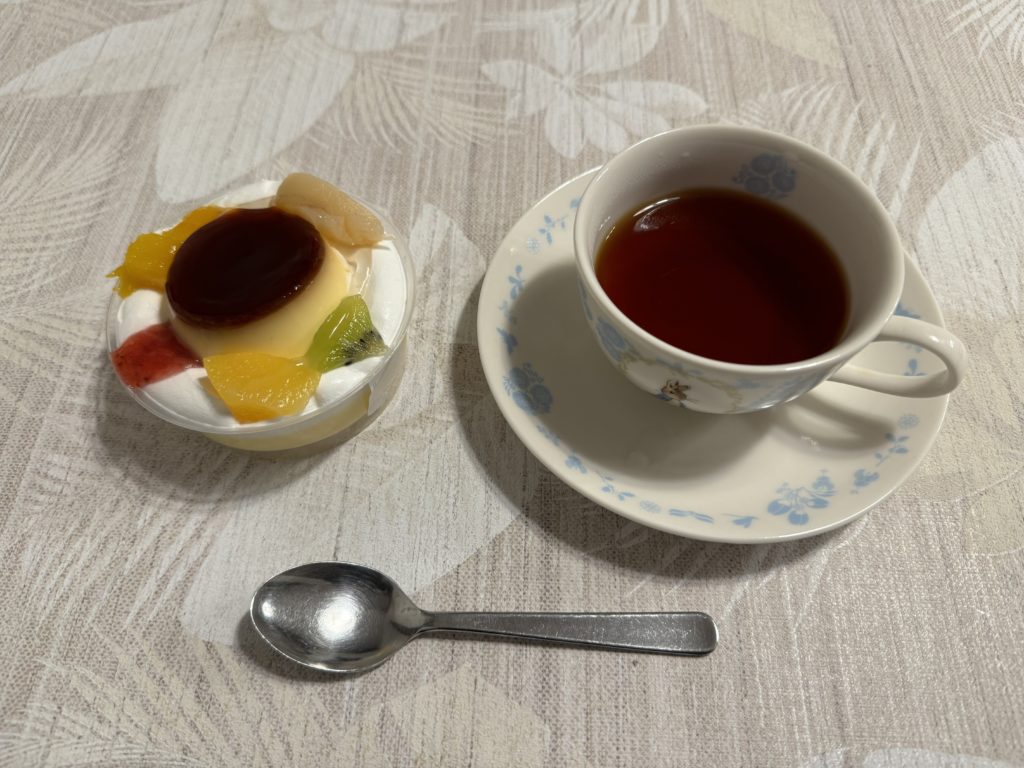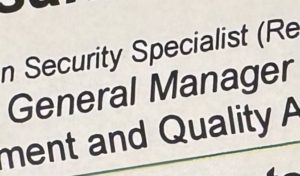
この4月を迎えるにあたり職場で人事異動があり、これまでいた所属部門の上位組織の責任者、つまり「部長」と称される役職についてしまいました。今在籍している会社では部が最大の組織単位となりますので、この役職は従業員として最上位のものとなり、大企業であれば本部長や執行役員などの役職とほぼ同等の役割も担うことになります。
私自身は大した学歴がなく、また職歴も新卒直後はITブラック四天王と言われる企業の一つへ何も考えずに就職してしまい大変な思いをし、その後、知人のつてですでに斜陽となりつつあった業界の零細企業に転職して社内の情報システム担当となり、紆余曲折があったにせよ今年で社内SEとして満25年、自分なりには頑張ってきたつもりであっても他と比べて決して立派というほどでもないものにも関わらず、それなりに羨望の眼差しを受けているであろう業界にある現所属企業でまさかこんな立場になれるとは、という喜ばしい気持ちと、本当にやっていけるのか、という不安が入り混じったまま、すでにおよそ二週間を迎えようとしています。
およそ九年半前に、副主任という下から二番目の役職―100人規模のプロジェクトをリーダーの立場で成功に導いたり、上場企業の経営企画室スタッフとしてほぼ一人で社内ITの企画と統括をおこなったなどのそれまでの経歴からすれば、自身としてはあまり納得感のない処遇―での入社となった現所属企業では、「こち亀での引退マラソンランナー鮫島のセリフ『ビリには追い抜く楽しみがある』の如く、低い立場であれば上へ這い上がる楽しみがあるともいえる」とのマインドのもと、自分にできることをとにかく何でも頑張ろうとのスタンスで仕事に励んだ結果、ちょうどコロナ禍の最初期だった五年前に中間管理職である課長に昇進したのですが、その時は「いやもう、自分にしては十分頑張った。この地位より上は孤独で辛いから現状維持でいこう」と思っていたのです。しかし、その結果としてあらゆることに張り合いが感じられなくなってつまらない、と思うようになっていったのでした。またコロナ禍ゆえの行動の制約があったりとか、更に年齢的に更年期の入り口だったこともあって精神的な均衡が保てなくなり、言わなくても良いことを周りに吹くようになって、本来であれば守るべき、大切なものも自らの失態により失うなど散々な状態に。そしてその後も胸を痛めるようなことがしばしば起きては精神的に追い詰められ「もうこれ以上の醜態をさらすのはダメだ、終わりにしよう」と考えだしたのが昨年秋。で、実際にジョブリターン制度を利用して、以前在籍していた企業へ転職活動を行い、相応の処遇案の提示と共に内定までいただいて先の年末を迎えることとなったのでした。
年が明けて本気で迷いに迷いました。「今の職場を去ってかつての自分を取り戻すのか」、それとも「今の職場でなんとか持ち堪えるのか」という選択肢のどちらを選ぶのか、ということを考えつつ、今後のことについて自身の上司を含むたくさんの方と相談し意見を伺いました。
それらの意見は、必ずしもいずれの選択肢を断定的に選ぶものではありませんでしたが、客観的に私が今の職場でどういう立ち位置にいるか、ということを知らしめられ、まだ新たな可能性が残っているのに敢えて落ちた砂を拾い上げオリフィスの上へ戻すような行為に自分自身が納得ができるのかどうか、ということを自らの心と対峙して真剣に考えました。
その答えは「否」。そして、「今の職場で持ち堪える、ではなく、今の職場で行けるところまで行ってみよう」、つまりは課長という立場に満足せず、その上を目指そうという前向きな気持ちになるきっかけになったのでした。結局、内定は辞退し「2025年度からは『現職場に再就職した』くらいの、新しい気持ちで頑張ろう」、そう心に決めたのでした。
その翌月、担当役員に呼び出され言われたのは「キミを来年度、新しい部長に推挙したい。受けてはもらえないだろうか。」でした。…いやまあ、確かに上を目指そうと決めたものの、まさかこんなに早いとは。しかし、気持ちはすでに決まっていたので回答には迷いはありませんでした。「頑張ります!」そして今日に至ります。
自分が新たに受け持つ部門は品質保証や知財管理なども行なっていて、社会に出てからIT一筋で来た私にとってはそれらの知識はあったとしても一般常識レベルがせいぜいで、到底専門家のレベルに達してはいないのですが、まあ逆に新たな知見を得られるチャンスとも言えるので、まずは新たに学ぶことから始めなければ、と思っているところです。
それから、部長と呼ばれるのは自分の人生で二度目になります。
一度目は40年前、当時通っていた少年剣道教室の児童代表になった際でした。「いやそれ、全然違うやん」というツッコミが入りそうですし、もちろん求められているものも全く違うことは理解はしています。ですが、自分の中では人生初めてのリーダーシップの経験がまさにそれであったことから、それ以降の人生の中で全く繋がりがない出来事だったとは思っていません。そして、その時は同じ地区の他教室の部長たちとの実力差を強く感じていたがゆえに、「大した実力もないのに」とか、「教室にとって汚点になってしまったのでは」とその後もずっと心に引っかかっていたのですが、平成17年にその教室の記念式典があり、かつての先生(かつて某国立研究所の所長をされていたほどの立派な先生でした)とお会いした際に、「確かにうまくはなかったが、一生懸命だった。だからみんなついていった」と当時の私を評してくださったことで、それまでのもやもやとしたものが晴れた気分になりました。
今の職場の私以外の部長職の方は学歴・職歴ともに凄まじい猛者ばかりで本当に私なぞが同じ役職でいいのか?どうする?という気持ちは当時のそれとあまり変わりなかったりするのですが、そういった弱点があるにせよ、自分の取り柄は「一生懸命」なのでしょうから、まずは気後れすることなくひとえに会社、そしてその事業を通じて我が国の科学技術への貢献ができるよう一生懸命頑張っていきたいと考えています。