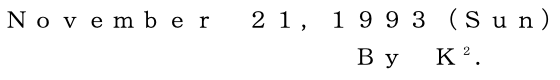昨晩、職場の若手と少し議論になった。
その若手の言は「私たちの世代は未来に何の期待も持てない」、「このような状況下で子供を持つとか、そんなことを考えることもできない」、「今日子供を持つ家庭は可哀想。憐れみではないけれど、大変だろうな、とは思う。」とのことだったが、私はその、少なくとも年齢で言えば半分余りの若手の発言には納得ができなくて、大人気もなく言い返してしまった。「世代世代というけれど、私たちだって氷河期世代だから、社会環境そのものはキミたちの世代とそう大きくは変わっていない」、「(私の置かれた環境が)可哀想、とか言われるも、私自身は実際にそう感じたことはない。そういう価値観はない」
きっとそれらの言葉は相手には響かなかっただろうし、むしろ上から目線の意見に聞こえ不愉快にさせただけだろう、とは思うけれど、私はこれを言わずにはいられなかった。なぜなら、私は自身が置かれている世代を理由に自らの不幸を語られることを好まない、端的に言えば「嫌い」だからだ。このように自らの境遇を世代のせいと転嫁するような発言は、この若手に限らず私と同年代の方も含め幾人かから繰り返し耳にしているが、その度に私は前述のように反論をし続けている。
そもそもこの世代なる言葉は誰が言い出したのだろうか。
団塊、バブル、氷河期、Z…などという括りがあること自体はよく知っているし、それらの特徴もググればいくらでも出てくるが、実際には目に見える形で年齢ごとの境界があるわけでもなく、それらは本来連続的なものである。おそらくはマーケティングなどの販売戦略を立てる際のターゲットを指す言葉として都合よく生み出されたのではないのだろうか(詳しく調べていないので間違っているかもしれないが)。仮にそうだとすれば、それは単に社会をマクロで見るときの一方的で、ときに偏見の含まれうるカテゴライズの一つでしかなく、それ自体は自らが歩む人生そのものには直接的な関連はないと私は考える。むしろ、それを自らと関連させて意識することは、本来得るべき知見に誤った解釈を与えかねず、文化の継承という観点で分断という悪影響すら生じかねない。
確かに時機として幸・不幸というのはある。例えば自然災害や戦争など、一個人ではどうすることもできない困難な状況はあるし、仮にそれで何らかの損害を被ったとすれば大変残念で気の毒なことだとは思う。しかし、それらは程度の大小はあるにせよ、世代に関係なく起こりうることであるから、それ自体が世代なる括りとはあまり直接的な関係はないと考える。勿論、間接的にそれらがもたらした結果が社会へ影響し、その時期に発育した人たちの環境や価値観を変えること自体は否定しない。しかし、その変化自体はむしろ世代という括りではあまりに大雑把すぎるように私は感じるのだ。
きっと本か何かで読んだのだと思うのだけれど、「生きることとは光を求めて闇夜を彷徨うようなもの」との考え方があった。私自身は正直、このような考えを持つことを若い頃は否定的だった。闇を彷徨うだなんて仮に光が見えていたとしても絶望しかないのでは、と感じたからだ。
しかし、今日までの自分の人生を俯瞰した時、実はその考え方が大筋では外れていないことを実感する。唯一かつてと解釈が異なるのは、それを絶望と取るか、それとも新たな冒険と感じられるかの違いだけかも知れない。私自身としては加齢と共にその見える光の数はだいぶ減ったように感じるが、まだ、その輝きは失われてはいないと信じる。
世代なる括りによってその闇と光の種類や数は異なることはあるのかも知れないが、しかし、光そのものが完全に失われたわけではないと思う。もしそれに疑念を抱くことがあるとすれば、きちんと光の存在を信じてその中に自らがいることを実感できているのか、それとも目を瞑ってあたかも「ない」ことにしてしまうのか、ということではなかろうか。ただ、それは個々人の選択であって、世代のせいではない。
冒頭の議論になった若手よりまだ私が若かった頃、初秋の奥日光戦場ヶ原で満天の星空を見た。「夜空というのはこんなに明るかったのか」と感動し、多数の瞬く星たち、時折空を流れる星に暫し見入ったことを今でもよく覚えている。
残念なことにその後ITの仕事を始めて以来視力が落ちてしまい、その星空を裸眼で楽しむ能力は失われてしまったが、それを補うべく高感度なミラーレスカメラで星空を撮り始めたのが昨年末のこと。自らにとって新たな星、即ち闇夜の光を見つけられるかも知れないと考えてのことだった。
かくの如く、自らではできなくとも代替の何かで新たな光は得られる。私は、その代替が私たちに続く人たちであってほしいし、そう信じている。
願わくば、その若手も自らの星をつかまんことを。